BLOG ブログ
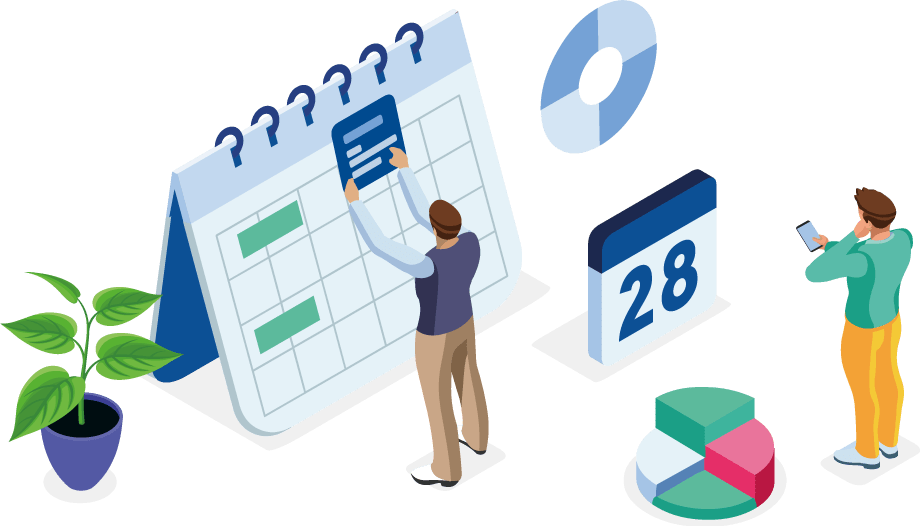

 映画『チョコレートドーナツ』から見る障害者問題
映画『チョコレートドーナツ』から見る障害者問題
障害者(マイノリティ)を題材とした映画やドラマ、小説などからみる障害者の問題について考えます。障害者をテーマにした物語もしくは登場人物として描かれているものは、レンタルビデオ店へ行けば必ず一つは見つけることができます。
障害者は“感動”の題材に使用されることが多く、涙を誘います。確かに、困難な状況下においてひたむきにあきらめずに歩む姿、もしくは障害を乗り越える姿には、自分自身を重ねて感動します。もちろんそれは障害者を題材にした映画に限っていえることではないですし、決して悪い事ではないと思います。しかし、障害者が訴えかける社会への問題点も見えてきます。
今日は映画『チョコレートドーナツ』から見る障害者問題を考えたいと思います。
この映画はアメリカ合衆国1970年代が舞台となっています。やや脚色はされていますがノンフィクションです。同性愛者(ゲイ)の二人のカップルが主役です。そしてダウン症の男児との3人の関係がテーマになっています。
今でこそセクシャルマイノリティが堂々と公言できる時代になりましたが、(日本ではまだまだという声は多くあります)70年代は差別、偏見の対象でした。会社でセクシャルマイノリティであることが知られてしまえば、解雇される、子が親にカミングアウトすると縁を切られてしまう、そんな時代でした。物語では弁護士とシンガーという職業で描かれていますが、やはり弁護士の男性は自分が“ゲイ”であることをひたすらに隠そうとします。仕事を失ってしまうからです。しかしシンガーの男性は自分のマイノリティを堂々と公言しています。次第に二人はお互いを深く理解するようになります。
愛し合う二人はある日、育児放棄(児童虐待)されているダウン症の男児を保護します。食事もろくに与えられず、母親は薬物中毒者、町をさまよい歩いている男児に対して二人は救いの手を差し伸べます。シンガーの男性は彼に温かい食事を、歌を。弁護士の男性は勉強を、言葉を。なにより男児は初めて“愛情”というものを知ります。
社会から虐げられている二人は男児に対してどのような感情を抱いたのでしょうか。3人でのささやかな暮らしが始まります。
しかし、社会はそれを認めようとしません。周囲の目も冷淡でついに児童養護施設と裁判沙汰になってしまいます。
堂々と二人は法廷で争いますが男児の為の裁判であるのに、二人がゲイであることばかりが問題視されます。『誰のための裁判なんだ!』『何のためにこの裁判をやっているんだ!なぜ公平に見てくれないのだ!』と訴えます。しかし訴えむなしく、男児は二人の正式な養子とは認められませんでした。
男児は施設へ引き取られ、そして脱走をし、町をさまよい歩き、ある日橋のたもとで亡くなっているところを発見されます。
男性二人は裁判に関わった人、全員に手紙を書きます。『あなたがたには、たかが一つの裁判だったかもしれないが、人、一人の命の為の裁判であった』と。
映画はそこで終わっています。
ハッピーエンドではありません。
この映画は感動の涙では終わりません。最悪な結果になってしまい、そこで突然終わってしまいます。決して名だたる名作のような最後ではないのです。
私たちは観た後に何を感じるのか、マイノリティは果たして“危害を加えるのか”違うというのであれば、なぜ今も苦しんでいる人達がいるのか。
日頃、障害者と関わる機会がない、福祉とは何の縁もない、そういう人こそ観て、そして感じてほしい映画となっています。
ブライトでは今後、スタッフ研修の一環としてこのような題材を取り上げ、意見を交換し合ったり、また現代に置き換えて支援にはどのようなことが考えられたかなど、様々な内容を話し合いたいと考えています。
映画は心を深め、豊かにしてくれます。今後も『マイノリティ』について考える映画をご紹介していきたいと思います。
